|
|
| 作品紹介 |
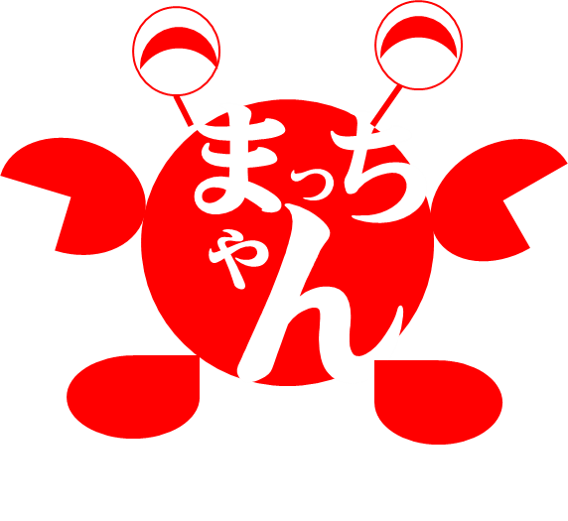
「桃源郷」(上)西遷編からご紹介致します。時は12世紀、1120〜1124頃のお話です。中国は西夏、北宋、南宋、遼(契丹)、金(女真)、中東は、アッバース朝(アラブ)、セルジューク朝、ヨーロッパは、ビザンティン帝国、神聖ローマ帝国、そして日本は平安時代になります。
この時代、契丹(大遼国)は、遼に服属していた女真族に反旗を翻され瀕死の状況であった。女真は後に自立し、国を建て金と称した。そして女真族の首長阿骨打(アクダ)が初代皇帝になるのです。
(数百年後、金はモンゴルに滅ぼされるが、女真族の金は後金と称して漢族圏を支配すると清と名乗り変えた。内容より引用すると、その理由は、北宋を滅ぼした時の、金の仕打ちを漢族が恨んでいることを考慮して金ばかりか女真という民族名も禁句にして満州族と称した。)
さて、話を始めましょう。
この様な背景の中、遼の皇族の耶律大石は西域へ逃れて活路を見出す為の使者として陶羽と白中岳を西へ向かわせました。
(耶律大石は後に、西遼を創設します。)
白中岳は西の契丹の同族への協力要請の為の使者として、陶羽は大食(タージ:アラブ)への使者として陸路、海路を使って西へ西へと移動する壮大な旅にでるのです。
時を遡ること秦の始皇帝の時代、暴政の為、賢者達は世を避けて身を隠した。時代は替わり漢の時代になっても一部の逃避行者は絶境に隠れ住み続けた。その地を桃源郷(上界)と言います。ある時代下界の状況を把握する為に探界使を派遣しました。その末裔が陶羽と白中岳だったのです。
彼らは、西域セルジューク朝のアラムート(イラン北部、エルブールズ山中アラムート渓谷の岩山の要塞:鷲の巣城)の長老ハッサン・サッバーフ(シーア派の過激派=イスマイル派)にとらえられ、その後、同士として迎え入れられます。
【注】Wikipediaより少し引用
シーア派:ムハンマドと血のつながりのあるアリーと、その子孫から選ぶべきだ「シーア・アリー(アリーに従え)」との考えを持つ人が多い集団
スンナ派:血の繋がりではなく、合意により選出すべきだ、と考える人たち。ムハンマドの教え「スンナ(慣行))」を重視すべきと考える人が多い集団
実は長老ハッサン、耶律大石、陶羽、白中岳、さらにはウマル・ハイヤーム(四行詩人、大学者、ニーシャプール天文台長)らは虐げられてきたマニ教信者の関係者で同士だったのです。彼らは姿を変え、宗教を偽り、隠れマニ信者として生きながらえてきたのでした。
マニ教を陰で支えてきたアラムートの長老ですが老齢故、他界してしまいます。求心力を失った隠れマニ教の行方は如何に・・・・? 東遷篇へと話しは続きます。
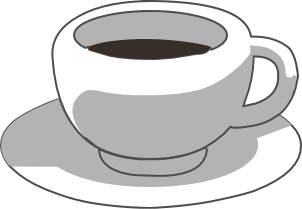
|
|

